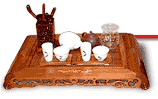|
|
|
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町2番1号CHATEAU黒田2F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勉強会について イベントについて 中国茶の分類について 中国茶の飲み方について ○2004年9月、中国語を学ぶ仲間がこの「清香館」を発足。 中国語の学力を維持させるため、中国茶を通して立ち上げました。 ○
会員は月1回、中国茶に関する学習会に参加し、知識を深めています。 ○
中国茶に関する歴史、茶名の由来や伝説について ○
中国茶葉の生産地について
○
有名中国茶による工夫茶の淹れ方について ○ 茶葉の色、形、を丹念に見たあと、茶水の味、香り、色についても詳細に確認します。 ○最後に各自感想を残しておきます。 感想欄 ○ 中国茶には数百種の茶葉があると聞き驚いてしまいます。また、茶道具もたくさんありますね。 ○ 中国茶には、心をリラックスさせる力があり会話もはずむようです。 |
2004年から1年半、内モンゴル自治区のフフホト市に語学留学していました。北京から飛行機で1時間位のところですが、上海や北京と違って田舎です。 現地の中国語の先生は上海とフフホトの差は10年と言っていました。文化、経済、全てにおいてフフホトは10年遅れているというのです。それでも不便さも楽しい1年半でした。 お茶にまつわる話を少し紹介します。 ■茶芸館やコーヒーショップ いつ行っても閑古鳥でした。値段がとても高いので一般の人は行きません。我々留学生はたまに贅沢したくて時々行きましたが、金持ちの現地の人か外国人しか来ないという印象です。例えば3人でお昼ごはんおなかいっぱい食べて20元。コーヒーショップでコーヒー 1杯20元。現地の物価に慣れてくると「たまの贅沢」になるのも理解いただけると思います。茶芸館はたいてい怪しい飾り付けがしてあり怖くて入ったことがありません。客が入っている様子もないのでなおさら入りにくく感じました。 ■ お湯を飲む 教室で水筒を持つ先生に何を飲んでいるのか聞いたことがあります。 答えは「お湯」でした。先生いわくお茶を飲むより体にいいそうです。ルームメイトもお湯をいつも飲んでいました。茶葉は家にありません。彼女は夏になるとお湯を冷ましてペットボトルにいれて凍らして朝持って出かけていました。ジュースはよく飲んでいました。変わったところではダイエット茶と暑気払いのお茶(両方とも粉末)を飲んでいました。私はスーパーでいろいろな茶葉を買って飲んでいました。 ■モンゴル族の人たち レストランではたいてい味も色もなくなったジャスミン茶がだされますが、モンゴル料理屋では別にミルク茶を頼みます。たいていどん、と魔法瓶ひとつでてきます。 お茶をつくりミルクと塩を加えて煮たものです。日本人は嫌いな人が多いようです。 店では茶葉はレンガ茶を使います。店の前で店員が茶葉の入った袋を地べたに置き金槌でガンガン割っているのを見たことがあります。モンゴル族の友人はレンガ茶はゴミが混ざっていて品質が悪いものが多いので紅茶を使うと言っていました。モンゴル族の人々にとってミルク茶は朝ごはんです。干した牛肉やきび、乳製品を入れて飲みます。栄養たっぷり、おなかいっぱいになります。 ■インスタントミルク茶 スーパーに「ミロ」みたいな感じで売っています。私は毎朝本格的に作るのが面倒なのでよくこの粉末を買っていました。味はまずいです。モンゴル族の人々も声をそろえてアレはまずい、と言っていました。ただお土産にはテキトーなモノだろうということです。 味噌汁ではないけれどミルク茶も家庭の味で、各家庭、レストランで味が違います。ここのは濃い、あそこのは薄めだなどなど。とにかくやはり手作りのものはおいしいです。 花房 8月30日のご報告及び感想: 8月9日〜17日 メンバーの3人が北京に行って、中級茶芸師の勉強と試験を受けました。資格試験の結果は9月中旬に分かります。 ドキドキですが、楽しみにしています!!! 技 能 試 験 中 試 験 後
中国茶 茶芸を学びに 八月九日から十七日の日程で、北京に行って来ました。観光のためではありません。中国語を通しての仲間と茶芸を学びに馬連道の「御茶園」まで足を運び、茶芸を学びに行ってまいりました。 はじめから初級のクラスを受講させていただこうと思い私だけが軽い気持ちで行きました。私は内心「二年も仲間同士で茶芸をやってきたし、ある程度出来るでしょう…」と。 「後悔は先に立たず」といいますが、後悔している時間はなく、とりあえず茶芸師の動作を見てノートに書き残します。中国語の講義内容を聞き漏らさないようにと努力はするのですが、まったくといっていいほど聞き取れません。 いつまでもへこんでいてもどうにもならないので、ここでは自分の出来ることをしっかり学んで帰るしかない。こう気持ちを切り替えなければなりませんでした。そう考えること以外には方法はありませんでした。もう翌日には、試験が迫っていました。 短い学生気分もつかの間。覚えなければならないこともたくさんあるのに、 「御茶園」につくと、受講者たちが今日のために準備していたチャイナドレスを着て待っていました。周囲の人達の表情には余裕があるように思えました。 実技、質疑応答など、どれをとっても緊張の時間が張り詰め、ひとつをクリアーするたび、「あと少し」、「もうちょっと頑張る」と自分に言い聞かせながら、椅子に座ることなく緊張の連続で、受験生の様子を眺めていました。 試験日の恥ずかしい思いは忘れないでおこう。どのようなことも自分が納得するまで研磨してゆくことが必要だ!(何事においても集中すること)。この気持ちを心に刻んで帰国しました。今回の北京は「逃げ出し寸前」の研修でした。観光だけの北京でしたら楽しい思い出だけが残ったでしょう。 苦しい思い出も出来たことは私には今後、何か得られそうな気がするのです。研修の効果は今後、どのような形で現れるのでしょうか。 副チーフ 2006.8.30 |
印度のお茶 韓国のお茶、中国の青茶 鉄びんの水湯の比べ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国茶の分類について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国茶は、その発酵度合いによって呼び名が変わりますが、それぞれの発酵段階での茶葉の色から名前がつけられています。
■もっと詳しい情報は、中国茶王国「彩香」の中国茶大図鑑でどうぞ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国茶の飲み方について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
All Rights Reserved. Copyright(C) 1999年〜2006年 EAST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






 蓋碗
蓋碗  茶壺
茶壺  グラス
グラス